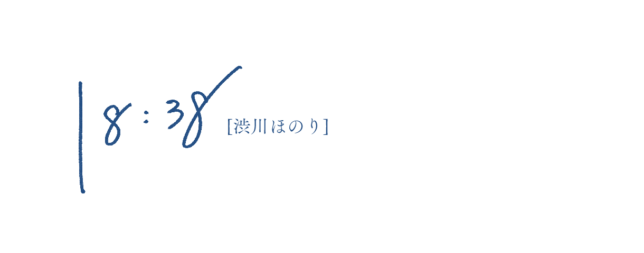初めて彼女を観た夜、アコースティックギターを弾きながら歌う彼女の声は美しく、演奏もやはり綺麗だったが、そもそも僕はギターが専門外で、上手いけれど上手いということしかわからなかった。そこに至るまで何年ギターを持てばいいのか、その凄さがどれほどのものか、想像出来るほど知識がなかった。
だけれど、その出番からほんのふたつ後。4人バンドの急なサポートで、とドラムセットの内側におさまっていた彼女の演奏は、僕の知識と経験とほんの僅かにあった自負に引火して、これ以上ない強さと勢いで僕を焼き、叩きのめした。
どれだけ陳腐だと言われてもいい。
高嶋永句は、本物の天才だ。
その演奏に、その歌詞に、そのコードにその声に、絶望しないことはない。彼女はただ美しい音楽を愛しているのではなかった。頭蓋を殴るような激しいもの、顔をしかめたくなる引きつったもの、聞き逃してしまうほどのささやかなもの、稚拙なもの、半端なもの、未完成のもの、繰り返しアレンジされたもの、そのすべてを尊んだ。彼女の世界にあふれる音楽は、間違いなく彼女の人生と視界を彩り、間違いなく彼女の才能を押し上げる。
僕がなりたいものに、彼女はいとも容易くなれてしまう。
悔しい、とすら思えなかった。ただ、消えてしまいたかった。彼女がただ生きてただ歌ってただ奏でているそれだけで、僕は劣等感に身を焦がす。卑屈になりながら、叩くことをやめられない。地獄みたいだ。
――お前の演奏は僕を馬鹿にしてるんだ。
去年の秋、僕は衝動的にそう言った。貰ったデモ音源を再現しきれず、いっぱいいっぱいだった感情が壊れて、「悩んでいるなら手伝うよ」と悪意なくやってきてくれた彼女を殴りつけた。言葉は自分の心に跳ね返って、自分の音の価値すら貶め、腐らせる。
彼女はあのときも、静かな顔をしていた。
薄い膜越しに話しているような遠さのまま、「ごめんね」と、息を震わせてうつむく僕を見つめていた。
「この曲はほのりの演奏を聞いてるときにきこえたんだよ」
アルバムのインスト曲について、彼女は屈託なく話した。身勝手な感情をぶつけた僕に対しても、彼女は音楽で交流をとり続けてくれたし、今も僕の音を褒めてくれる。どんな音楽も、彼女にとっては美しい。そこに人間の美醜や善悪は無かった。
「ほのりの音は真面目で、楽曲に寄り添ってるのがいつもわかる。突っ走ったりしないんだよ。だから曲のまとまりが出て、目立ちたがりな兄さんのギターとか、ちょっとめんどくさがりで引っ込みがちな偲のベースとかとあわせても、すごく調和がとれてる。こないだのライブを観てたときにね……」