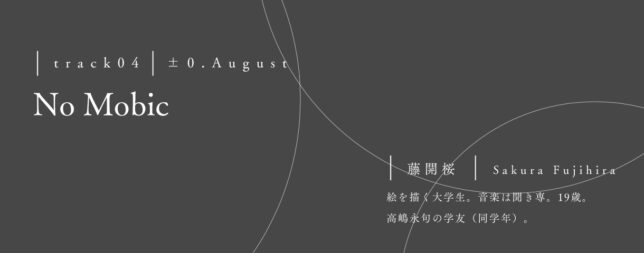大学に入って出来た友達の中でも、高嶋永句は群を抜いておかしかった。
始まりはと言えば、大学に入ってひと月ほど経ってから開かれた学部の新歓だった。男たちに群がられていたその夜一番の美人である彼女は、すべての言葉に短く頷き答えながら、隣に座るわたしに「藤開(ふじひら)さん、おかわりいる?」「なにか食べる?」と声をかけてくれた。
ちやほやされてしかるべき圧倒的な容姿に驕るどころか、横の女を気遣うことが出来るだなんてと感心しながら、いらないだのいるだの簡素な返事を寄越していた。当時のわたしはあまり経験の無い酒がだいぶ回っていて、眠くなり始めていた。
隣でわたしの五倍くらいの酒をぱかぱか飲んでいく高嶋永句は、水しか飲んでないみたいに素面だった。実際酔っていたのかもしれんとその時は思っていたけど、あとからその夜の話をした際に間違いなく素面だったのを確信した。恐ろしい女だ。
彼女にたかっていた男たちはその横で酔い始めたわたしを見て、ちらちらと照準を変え始めた。何があってもなびかないし動じない鋼の美人より、手軽で気軽で安易な女のほうが重宝されるってのは、滅茶苦茶不服だし不愉快ながらもある。わたしはファッションもメイクもアクセサリーも自分のためだけに買うけど、その認識は言ったところで理解されない。
案の定、彼女に対して会話のピッチングマシーンと化していた男がこちらを見る。
「藤開さん大丈夫?」
あー、と声に出したか出さなかったか、場がうるさかったのもあって覚えてない。
ただ、上ずった声と共に伸ばされた手はわたしに触れることなく叩き落された。
あまりにも突然、ばしんと不愛想な音が響いたので、一瞬で半分くらい酔いが醒めた。
先輩の手を容赦なく叩いて撃沈した蝿としたのは、隣の女だった。
ぱちぱち瞬きを繰り返しながら高嶋永句を見ると、困ったように下げられた眉に反して、びっくりするほど穏やかな微笑みを保っている。少なからず暴力を振るった人間とは思えない表情で、わたしの酔いはますます薄れる。
「……え、何? 高嶋さん」
当たり前に、手を叩かれた男は機嫌悪そうだった。声は低く、目の前の女を不快な生き物としているのがよくわかる。酒の効力が残るわたしですらちょっと喉の奥が重たい、あからさまなオーラを発している。パワハラの才能あるな。
高嶋永句は平然と、にこ、と目を細めて笑う。
「すみません、藤開さん具合悪そうだったので」
「うん、だから俺が介抱してあげようって思ったんだけど?」
疑問符にすら圧をつける男に、彼女は「はぁ」と気の抜けた相槌をうつ。
「さっき、女の子と寝た話をたくさんしてたので。添い寝じゃ介抱にならないと思います」
後日、ほかの学部のサークル仲間に聞いた話だけど、わたしに声をかけていた男はよその学部の新歓に出没するシモの当たり屋みたいな奴だったらしい。一緒に授業を受け昼飯をとる仲になった永句ちゃんは、昼食のサンドイッチを片手に「悪目立ちさせちゃってごめんね」と謝罪し、続けて「あのとき止められてよかった」と呟いた。
「あの人のこと、知ってたの?」
「ううん、なんにも」
「じゃあ、なんで止めたの」
隣り合えば友達だとか、そういうタイプの熱い人情を持ってるようには見えなかった。
彼女は少し首を傾けながら、「止めようかなって思ったの」と答える。
「きこえてきたうたが、桜(さくら)ちゃんとは合わない感じだったから」
「…………うた?」
耳慣れない表現を反芻するわたしに、彼女は軽く頷いた。
こんな話をしてしまうとまるでその「うた」とやらが彼女の異常性だ、と思われかねないが、高嶋永句がおかしいのは、この共感覚めいた第六感に因るものではない。わたしは平面上に展開される空想をこよなく愛する、つまるところオタクな生き物であるので、むしろその感覚については畏敬を持って受け止めている。
常人には謎の第六感を持つこの女は限りなく良く言えばドがつくほどの天然であり、忌憚なく言えば人の内心を推し測るのが下手だった。ド下手。つくほどじゃない。ドがつく。
しかも悲しいとか、悔しいとか、妬ましいとか、そういう人として生きる上で持っといたほうがいい感情に限って、理解度が致命的に低い。服装、持ち物、生活態度あたりから察する生育環境の穏やかさとは、あまりにも乖離する。何不自由ない家庭から出てくる本物の化物に、一歩間違えたらなれる。ならないだろうけど。
失うものがない人間を無敵と呼ぶけど、彼女は失う以前に育たないから無敵だった。
痛みを感じる神経が、さっぱり無いみたいに。
音楽活動をしているらしいこの友達は、話を聞く限り昔から何かと周囲に僻まれ、妬まれ、やっかまれて生きてきたっぽいのだが、本人がすべてを「そのとき聴こえたうたを書き出したのがこれでね」という調子でなんもない風に受け止めて通り過ぎているので、実情がまったくわからない。少なくとも楽器ケースで殴られたことがあるというのは事実として聞いた。音楽やる奴、どうかしてるんじゃないの。
わたしが音楽やってて、楽器ケースで殴られるようなことがあったら、絶対に辞めてる。
どんだけ才能があっても、賞賛されても。
永句ちゃんは「何も入ってなくてよかったよ」と穏やかにケース殴打事件の感想を述べた。
もっと言うことあるだろ。五億あるだろ。
永句ちゃんは生まれ持った天然素材メンタルがあらゆる方向にオリハルコンの強度を発揮していて、普通に音楽やってるけどまともな神経だったら辞めてそうな経験ばっかしてるし、普通に男とも話すけど男なんて十把一絡げに嫌悪して恐怖してもおかしくない経験を、してる。永句ちゃんの普通を否定したいわけじゃないが、どうしたってならせないズレはあって、わたしみたいに心配する奴もいれば怖がったり利用しようと考える奴もいて、彼女はそれでも大多数の人間に合わせて生きている。
その懸命な歩み寄りもあって、新歓で先輩の手を叩き落とし平然としていた割に、痛みも悲しみもわからなくて音楽ばっかりわかる割に、大学での永句ちゃんは別段浮いていない。もとがクソ美人で背も高くてスタイルがよくて高嶺の花嶋さんなので、親密って友達は少ないけど。わたしがいるし、とか言うのは傲慢なんかね。
そう、わたしは高嶋永句の友である。
彼女の見た目も、話し方も、変なとこも気に入っている。真面目で穏やかで人のことをめったに嫌わない性格を尊敬してる。わたしが家のこととかでちょっと僻みっぽいことを口走ったとき、諌めたりせずに聞き流して後で飯奢ってくれるとことか。突拍子もなく出かけようよ、と連絡を寄越してきてデパコス売り場に着いてから「桜ちゃん何が欲しい?」と単刀直入に誕プレリサーチしてくるとことか。デパコス買うのに日焼け止めとリップしか塗らない胆力も、そのせいでまず自分がコスメの使い方を教わって知識を地産地消してる抜け方も好ましい。
音楽のことはよく知らんが、音楽活動をしているというのはかなり早い段階で聞いた。ソロでやってて、一応CDとかもあるらしいんだけど最初の一枚をアホ価格で出して先人に相当絞られたらしく、売る気っていうか出す気しかないのがよくわかる。わたしがたまたま絵を描く人間で、音楽しか能の無い永句ちゃんより遥かに画面というものへの執着があったので、CDを出したりMVつけて動画出すときの手伝いもするようになった。音楽のことは今もよくわからんが、作曲ペースがぶっ壊れているんだろうな、ってのはアルバムの異様な頻度から察している。しかしこれでも控え目にしていた、している、らしい。かわいがってるだけのつもりが殺しちゃったときのライオンの言い訳じゃん。
高嶋永句の辞書に親友という文字はなさそうだが、音楽やってない人間の中ではトップランカーであると言える気がしている。CDのデザインの打ち合わせもあって休日も頻繁に会うし、飯を食うし、買い物行くし、ライブも観る。わたしはほかにも趣味なりなんなりで繋がってる友達がいるけど、友達の中でも永句ちゃんの優先度はそれなりに高い。
で、あるからには。
わたしがこの、天然で無敵でそれなのに無警戒である友達の虫よけになるつもりだった。
見知らぬ男に話すのも嫌になる酷いことをされたのに、顔と体だけ見て群がってくるゴミも多いのに、ライブなんか行くと一人の女の子を狙ってます感のすごいおっさんもいるのに、永句ちゃんは老若男女万人すべてが音楽のもとに平等だと思っている。
その認識を正すのは世界平和くらい難しい。
正すもなにも彼女と世界の接続は音楽によるのだから、どうしようもなく正しいのだ。
だから蚊帳が必要で、そんならわたしが蚊帳になろう、と思った。永句ちゃんの音楽関係の知り合いには詳しくない。よく知らん人にこいつの蚊帳を頼みます、とは言えない。わたしは口が悪く声がでかく怒りが心より早く顔に出るたちで、彼女にまとう虫の数々を振り払ってきた。なにかの功労賞もらえそう、と知り合いには言われたがほんとにそうだ。
でも、蚊帳の中に虫がいたら別だ。
「ありえんマジでありえん、ありえんアワード自薦してノミネートすんのやめてくれ」
大学二年生の夏休み、わたしは永句ちゃんととある人物を会わせるべく、待ち合わせ指定した新宿のルミネにあるレストランで叫んでいた。
永句ちゃんは運ばれてきた青いクリームソーダをつつき、
「桜ちゃん、もしかしていま怒ってる?」
のほほんと笑いながら、そんなことを言っている。こいつは妬みも悲しみもわかっていないがまずそもそも怒りへの理解度ステータスがドラクエ序盤のスライムより低い。きのぼうで滅多打ちにされるほど無い。
「怒ってるっていうか怒ってるし怒ってるだろ」
「なんで?」
「どう考えてもその人永句ちゃんのこと狙ってるじゃん」
「その人って……あぁ、天野さん」
一単語の代入を理解しただけで必要以上に納得しながら頷く友達に、わたしは頭を抱える。
理解されたいのはそこじゃねえのよ。
永句ちゃんは最近、最近ってのはここ二ヶ月くらい、会話にひとつの人名を出すことが急激に増えた。たった二ヶ月で夏休み入ってて大学で会う頻度は減ってるっていうのに、出会ってから今までで一番くらい聞いている。嘘、「桜ちゃん」の次に聞いている。
その「天野さん」はどうやら増えに増えていく永句ちゃんのCD在庫を心配し、よく使うライブハウスとうちの大学の真ん中にある自宅を荷物置きや作業場として使っていいよと、関係の浅そうな感じからは破格の態度で接している。実家暮らしの永句ちゃんは家より遥かに動きやすいその人の家によく通い、ショバ代を請求されないので代わりのように食事を作ったりして、最近はすっかり拠点のようになっている。故に会話の天野さんカウンターは右肩上がりで、今日もこないだ初めて泊まったせいなのか天野さんの家に永句ちゃんのヘアケア用品が用意されていて、髪の毛に無頓着な彼女がいたく感動したということだった。
わたしが「天野さんも髪長いの? 親切な人でよかったね」と打ち返したら、「天野さん、昔美容師学校行ってたんだって。俺の使わせるのも悪いなって思ったって言ってたよ」と剛速球の返答を食らい、わたしの疑念及びキレメーターが点火してしまった。
ベーシストだっけ、俺って言う女の人でベースはかっこいいね。
ううん、天野さん男の人だよ。
………………男?
うん、こないだ桜ちゃんも会ったでしょ、ゆらにテンポって言われてた人。
………………あの、マッシュっぽい髪の?
うん。もしかして天野さんとテンポさん別人だと思ってた?
あんた、いなかったじゃん。ゆらさんに説明任せて雪崩れたCDのほう行ってさ。
あ、そうだったねごめん「えっごめんじゃねえよいや言葉遮ってごめんなのはわたしなんだけどなんだそれ詐欺じゃん! レターパックだって詐欺断ってんだぞ!」
こんなとこである。「天野さん」を女性だと思って受け入れていたわたしは手酷く裏切られた気持ちになり、活火山の物真似をするに至った。永句ちゃんは天野さんを疑いキレるわたしに対して徹底抗戦の構えを見せるが、多分この場合は永句ちゃんのほうが分が悪い。だって、わたしが怒ってる理由も天野さんの本心とかも絶対なにひとつわかってないから。後者はお前もわかってねえだろっていうのは、置いとかせてほしい。
テンポと名乗っていたあの夜の青年を思い出す。髪が淡めのブラウンで、肌が白めで全体的に細くて、偏見マックス印象で言えば草食系っぽい。優男レベルカンストみたいな柔和な顔立ちをしていて、これでベーシストなんて死ぬほどモテそうだ、と感動すらしたのを憶えている。付き合っちゃまずい3Bなんてのを聞いたことがあるけど、その一角として不足ない感じだった。外見が草食系だからって中身がそうかはわからんだろ。
しかも、美容師学校卒。3Bビンゴリーチ。わたし自身は美容師のカスもバンドマンのクズも実在を知らないけど、知らなくたって警戒しろっていう先人の知恵は信じている。
「男であんたに優しくて家に呼んでてそれでヤリモクじゃない確率は限りなく低いでしょ」
語彙を考えて若干声のボリュームを落とすと、永句ちゃんは首をかしげる。
「ヤリモクってなに? シケモクの仲間?」
「シケモクわかってヤリモクわかんねえのかよ……」脱力しそうになる。「体目的ってこと」
「え、だから天野さんはそういう人じゃないって」
永句ちゃんは普段の穏やかで世界滅亡しても取り乱しませんみたいな態度がどこへやら、妙にむきになっている。
「そんなの永句ちゃんにわかると思えん」
「大体、男でも女でも危ない人は危ないよ。男の人だからって警戒しろっていうのは、」
「わたしは、永句ちゃんが二度も他人に害される人生送るのは嫌なの」
言われたくないだろうと明言を避けていたが、はっきり言わないと伝わらないと思った。
うつむき、頼んだ定食が運ばれてきて永句ちゃんがお礼を言う。トレイはわたしの前に置かれて、わたしは黙ったまま少し会釈をした。永句ちゃんが頼んだパスタもやってくる。
「……あの、桜ちゃん」
「なに」
「ありがとう、そう思ってくれて」
永句ちゃんの声は穏やかだった。わたしの無粋で無神経な意図のすべてが伝わってるかはともかく、多分わたしの焦りはわかっているのだろう。聴こえるうた、とやらで。
「でも、わたしが好きで行ってるから。心配してもいいんだけど、止めないでもいいよ」
ふふ、と笑い声が添えられそうな声音に、顔を上げる。
「……何が、好きで、行ってるって?」
「? 天野さんだけど」
パスタをフォークでくるくるしながら平然とそんなことを言うので、わたしはのろのろ持ち上げていた箸を落とした。永句ちゃんが「だ、大丈夫?」と店員さんを呼んでくれる最中、わたしは彼女の言葉を百回くらい反芻していた。
好きだから通っている。
好きだから一緒にいる。
そんな、どこにでもありそうな言葉。
ドラマチックなんてとんでもない、凡庸で、故に一番永句ちゃんから遠そうな理由。
新しい箸をもらって、定食に手をつける。
「……あぁ、なら、もういいんだけど……」
力が抜けて、口の端がゆがむ。我ながら結構ブスな笑顔を浮かべた気がする。
好きでそうしてても、止めなきゃいけない瞬間はもちろん、ある。
好きな相手だからって、無警戒に接していいかって。そりゃ否だ。
けど、永句ちゃんが好きでそうしたいって、人間に対してそんなこと言うだけで、もう、どんな宝石より稀有な瞬間を掘り当てちゃった気がする。
諦めのため息をつきながら定食のあんかけ唐揚げを食べるわたしに対して、パスタを食べる永句ちゃんはご機嫌である。天野さんについて友人のお墨付きを得たと思ってそうなので、墨はまだ付けねえぞと念を押しておかねばなるまい。
パスタを半分くらい食べたところで、永句ちゃんが「話、変わるけど」と切り出す。
「今日会わせたい人って、もうそろそろ来てる?」
あ、とわたしは机の端にチキンレースの如く引っかかっているスマホを見る。
ちょうど『つきました!』と連絡が来ていた。レストランフロアに来てもらえないか頼むと、素早く了解の返信が来る。スタンプを押して、永句ちゃんに向き直る。
「そうねごめん、そう、今着いたって連絡来てた」
「わぁ! 楽しみだな、桜ちゃんのお友達なんだっけ」
「友達っていうか、後輩だね。高校の。今三年なんだけど、進学予定なくて、夏休み暇らしくてさ。人好きするし物覚えバリバリにいいから、売り子とか頼めるかもって思って」
「ライブハウスとか好きなの?」
「好きとか以前に、全然行ったことないと思うよ」
「そっか……」
会話の糸口を喪失したせいかライブハウス仲間ではなかったせいか、肩を落としてしょげる永句ちゃんに、「すぐ好きになるよ」と声をかける。
永句ちゃんがその子をでも、逆でも、その子がライブハウスをでも、成り立つ言葉だ。
まもなく店の入口に、とことこと小柄な影が現れる。店員さんに声をかけている小さな背中に呼びかけると、腰の下まで垂らした黒髪を揺らして、振り向く。夏休みなので当然私服姿で、ミルキーブルーのワンピースに身を包んでいた。相変わらず手足が細いし、胸がでかい。真夏を忘れたように真っ白な肌で、なんとも絵に描きやすそうな女の子だ。わたしは絵を描く人間なのでそう思う。
光沢のある白いパンプスを鳴らして、席に近づいてくる。永句ちゃんのように誰もの目を問答無用で引く美少女ではないけど、ふっと花の匂いに振り向くような容貌。黒すぎて店のライトに容易く染まってしまう瞳が、花色に輝いている。
手を小さく振って、久しぶり、などと声をかける。
彼女――葵ちゃんは、わたしに軽く会釈をしてからまず、永句ちゃんに微笑んだ。
「こんにちは、はじめまして。三橋葵です」
「永句ちゃん、この子が葵ちゃん。かわいいでしょ……あれ」
挨拶された永句ちゃんを見ると、ぽかんと口をあけてフリーズしている。
え、何由来の石化?
わたしが眉をひそめ、葵ちゃんも首をかしげて「だいじょうぶですか?」と問う。背中を丸めて永句ちゃんの顔をそっと覗き込む葵ちゃんの肩から、黒髪がさら、とこぼれる。
それが栓を抜いたように、永句ちゃんが呟く。
「……花束……」
「え?」
「は?」
同時に疑問符を浮かべたわたしたちをほっぽって、一人で何かのボルテージを高めた永句ちゃんが葵ちゃんの手を掴む。お前そんなことする人間じゃなかっただろどうした。
「すごい! 花束みたいなうた!」
「え、えっと? 桜先輩」
助けを求める葵ちゃんに、申し訳なく思いながらも「あぁうん、これが高嶋永句ちゃん」と紹介する。まさか瞬間湯沸かし器よりも素早く変な人アピを完了させてしまうなんて。
葵ちゃんは物静かな音楽好きの美人としか聞いていなかった女に激しく手を掴まれて困惑していたけど、すぐに落ち着いて永句ちゃんに「パスタのびちゃいますよ」と笑いかけた。
肝の据わった子である。
そんなわけでわたし藤開桜は、おそらく生涯の友人となるであろう音楽狂いの女、高嶋永句の人間関係を案じつつ、わたしが知る中でも有数にまともな知人、三橋葵を紹介した。
程なくして高嶋永句の彼氏となった天野歩氏と顔を合わせ、3Bがリーチどころか1Hのオマケつき超ビンゴだと知って酒を吹き出してしまったのは、まぁ、笑い話だ。
written by Tohko KASUMI