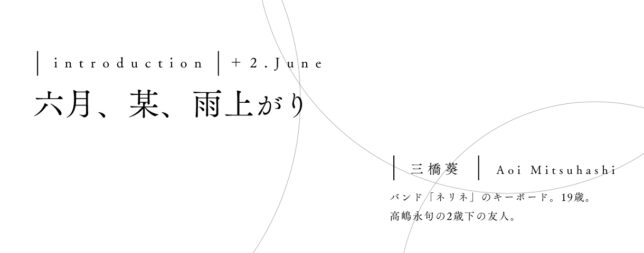二十七歳で死んだら伝説になれる。
なんて話をしたら、きっと彼女は「生きて伝説になろうよ」と言うだろう。
あっけらかんと、なんでもなく、ごく当たり前のことのように。
わたしたちの誰もが、二十七で死ぬことはない。半端な幕引きから生まれる音楽がどれだけ悲痛に輝いていても。彼女の音楽には二十七年なんてみじかすぎる。
東京、下北沢。あちこちで大なり小なりライブが行われている、六月の週末。ここリリクでも例にもれず、複数のバンドが色とりどりのライトに照らされながらステージに立っている。わたしは再来月に二十歳をむかえる予定で、アルコールは避けカルピスを持ってステージを眺めていた。赤色のライトがよく似合う、はげしい演奏がかっこいいバンドだ。
きのうから降りつづいていたなにもかもをのみこみ流しそうな雨はやみ、夕方からは嘘のように晴れた。雨に濡れながら苦労して楽器を搬入した出演者は、脱力しながらまぶしい夕陽を見たものだ。いまはそんなこと忘れたように楽器を鳴らし、声を嗄らし、観客と共に夜の重い熱気をつくっている。今夜のライブはもう終盤で、予定されていた演奏は現在ステージにいる四人で終わる。
……予定はね。
よく効いた空調が意味をなさないほど、スポットライトの熱はつよい。あの強烈な光はほんとうに皮膚をつらぬいてしまうのではないかと、浴びる側になったことがないわたしはひっそり不安になる。
わたしのすぐそばに立っている四人は演奏に聞き入っていて、花から甘い香りが漂うような、身体におさめきれない高揚感が伝わってくる。わたしは脳裏の鍵盤をなぞりながら、ステージ上できらめきをはなつバンドを食い入るようにみつめた。
わたしたちがあのまばゆい場所へあがるのは、このつぎだ。
最後の曲ですというMCのあと、ゆるやかに演奏がはじまる。
ベースの心地よい音が観客の耳を揺らす。
あぁ、ほんとうにいいのかな。
この一週間、飽きるほどくりかえした問いが舌ににじむ。べつに邪知暴虐の限りを尽くそうってわけではない。けど、わたし以外の全員がなんでか落ちつきすぎているのだ。ライブ経験があるなしではない、なにか精神的な違いを感じる。覚悟が決まっちゃってるというか。
芸術家ってある程度ぶっとんでるもんなのかな。
そんな考えはおそらく一ミリも伝わっていないだろう、眼前の高嶋(たかしま)永句(ながく)が振りむく。
花が開くようにほほえみ、澄んだ声でささやく。
「これ新曲だ。ベースから始まるの、いいね」
心底楽しそうな声音に、すこし笑いそうになる。
緊張も躊躇いも戸惑いも、彼女には無縁だ。いまこのときの演奏を、楽しむことしかしていない。いっそ清々しいまである。
揃いの白い服を着たわたしを含む四人が、青いエレキギターに寄り添う高嶋永句を見る。彼女はいつも通り、白い芍薬の匂いをまとって立っていた。
その存在が誰かにとって唯一の芸術であるように。
彼女もきっと、この場すべての音楽をきいていた。
イントロを称賛された新曲を歌いきり、ギターボーカルが曲名と感謝を述べる。
高嶋永句はごく自然に、水の流れに沿って歩き出すような身軽さで、ギターを持ち直してステージに向き直った。いつも通りの笑顔を浮かべる。
「じゃあ、行こっか」
わたしが所属することになった、なってしまったバンドはネリネと言う。
ベース、天野(あまの)歩(あゆむ)。ドラム、中村(なかむら)優良(ゆら)と木暮(こぐれ)彰(あきら)。キーボードにわたし、三橋(みつはし)葵(あおい)。ギターボーカルと、ほか必要な楽器のすべてを担う高嶋永句。彼女がリーダーにして主犯だ。
発足はびっくりするほど唐突で、名前も最初集まったときにどうするって話が出て、メンバー全員の案から決めるはずが道中の花屋で見かけたダイヤモンドリリ―……ネリネを思い浮かべて発言したわたし以外まともに単語ひとつ出さなくて、そのようになった。
ここまで適当すぎるけど、逆に言えば適当なのはスタートダッシュだけだった。
社会人が多い顔ぶれながらもまめに集まって合わせ練習を行い、唯一ほぼ素人のわたしはとにかくキーボードをまともに弾けるまで練習した。暇さえあれば永句ちゃんが付き合ってくれたのは助かったけど、はやく釈放されたいと思う日もあった。
春先に生まれたネリネのお披露目を行う初ライブとして、永句ちゃんは六月末にリリクで行われるブッキングライブをあげた。出演するバンドが名前をあげられていく。わたし以外のメンバーはちらほらと顔見知りがいるらしく、へぇとかほぉとか言いながら聞いていた。わたしは暗譜した曲を脳内で流していた。本物の素人ゆえ、知ってるひとがほとんどいないので、逆に気楽だ。
ライブで演奏する曲は三曲、多分これとこれとこれで、お金はわたしのほうでなんとかするけど、知り合いで来れそうなひといたら声かけてね、と、永句ちゃんはうきうき話した。
またもへぇとかほぉとか言って、その話はあっさり終わった。わたしは演奏予定のうちひとつが結構むずかしい曲だったのを思いだして、なんとも言えない顔をしていた。
ネリネのメンバーは冷静沈着というか、大抵のことに動じないひとしかいない。ドラムであるゆらと木暮さんはどっしり構えるタイプでその態度に見合う度量があるし、ベースのテンポは何事にも線引きをして離れた位置から眺めていることが多い。わたしも自分で言うことじゃないけど、同年代と比べて落ちついてるほうだと思う。
その全員が、ライブ一週間前になって取り乱した。
わたしと永句ちゃん以外はネリネのほかにも持ちバンドがある。追い込み練習をするスタジオに現れた木暮さんが、べつのライブハウスで企画に出たときもらったチラシを床に置き、神妙な顔でつぶやいた。
「ネリネの名前がない」
永句ちゃんはバイトが長引いて遅れるらしく、まだいなかった。
寡黙で、おおきな岩のように穏やかな木暮さんには珍しく、しきりにまばたきしている。
「いやいやうちの店長が作ってんのよこれ、そんなヘマ、………………ないわ」
ゆらはリリクのスタッフでもあるので、二重の意味で衝撃を受けているらしく「え、ないんだけど?」と事実を反芻していた。わたしとテンポもぴかぴかの床にのびているチラシを覗き込み、出演者一覧を読む。テンポはちいさく声に出して読んでいた。
「……な、ない。ほんとにない」
「一応裏面見ていい?」冷静を装っているけどテンポの声も困惑していた。「……ないね」
「――なにがないの?」
過剰に澄んだ声に、四人が振り返る。青いギターケースを背負った永句ちゃんが、口元にちいさく笑みを浮かべて立っていた。
ネリネのベーシストで違うバンドでもベーシストで永句ちゃんの彼氏でもあるテンポが立ちあがり、代表して「永句、あのさ」と声をかける。
「これ、来週のライブのチラシ。木暮くんがよその箱でもらってきたんだって」
「あ、わたしも昨日もらってきたよ! もうすぐって感じするね」
「うん楽しみだね。でさ、このチラシにネリネの名前がないんだけど」
「そうだね、飛び入り扱いにしてもらってるから」
「……え、飛び入り?」
最後の一言はわたしである。テンポもゆらも木暮さんも気持ちは同じだったのか、一瞬黙る。永句ちゃんだけいまにも飛び跳ねそうにテンションが高い。
「リリクにも出演のバンドにも言ってあるから、迷惑はかけないよ! 安心して!」
「なんで許可とってまで飛び入り……?」
ほかのみんなは硬直したままなので、わたしが尋ねた。ライブに飛び入りで現れて劇的な幕上げを行う、真新しいバンド。想像出来なくはないけど、許可をとって出演を決めるならわざわざ飛び入りの形にしなくてもいいんじゃないか。バンドマンの中ではそれが通常ってことも、みんなをみる限りなさそうだし。
永句ちゃんはふしぎそうに首をかしげる。
当たり前のことを再確認するように、
「そっちのほうが劇的じゃない?」
清流の水音に似た声で、わたしたちの常識的かつ社会的な考えは押し流される。
「せっかくなんだから、伝説になろうよ。出来るだけ派手に、最高に、劇的に飛び出そう?」
大丈夫だよ、と永句ちゃんは笑う。
なにがだいじょうぶなのかなんもだいじょうぶじゃないのか正気の頭で返答を考えていると、テンポが「確かにそうだね」と言い出す。嘘でしょ正気捨てちゃったの、とテンポをみるとその横からドラムふたりも「そらそうだ」「迷惑かけないから、劇的にこしたことないな」とうなずく。
「え、えぇ」
わたしだけが困惑していたけど、永句ちゃんがわたしと目を合わせてはっきり「大丈夫」と言い切るので、納得してなくてもうなずくほかなかった。だいじょうぶかどうか、考えるのも無駄な気がしたし。
当日の夜、チラシに名前が載っていた出演者の最後であるバンドのボーカルが、「もうちょっと残っててくれな!」とありがたい言葉を残してステージを降りた。チラシではトリになっているこのバンドは永句ちゃんとかなりなかよしみたいで、ネリネの練習にお菓子まで持ってきてくれた。ネリネの結成をわたしよりずっとよろこんでいるみたいだ。
薄暗い中で楽器の搬入をしてステージにあがると、視線と一緒に気分の段階が切り替わる。みおろす客席は思っていたよりずっとまっくらで、違う世界みたいで、それなのにひとの顔がよくみえた。キーボードのわたしはステージの端に近い場所に立つ。中央に永句ちゃんが立って、テンポもゆらも木暮さんも位置につく。ドラムセットを無理やりふたつのっけているので手狭だけど、たぶんすぐにそんなこと考えていられなくなる。
チューニングを済ませて、コーラスを担うわたしとテンポを含めたマイクの位置を合わせて、永句ちゃんはわたしたちを振り返る。こんなときなのに、こんなときでも、永句ちゃんは透明な水のように穏やかで、きれいにほほえんでいる。全員がうなずく。
すべての明かりが落ちて、宵闇よりも深い黒が一面を塗りつぶす。
ギターの音が、世界をはじめる合図のように鳴る。
「こんばんは、ネリネです」
すべてのライトが彼女を照らした。
written by Tohko KASUMI